最近ニュースで耳にする「相互関税」。
でもこれって、そもそもどんな仕組みでしょうか?

関税はわかるけど、「相互」?
トランプ大統領がよく使っていますが、以前からあった言葉でしょうか。
この記事では、関税の基本から相互関税の意味、そして私たちの生活にどう関係してくるかまで、やさしくコンパクトに解説します。
難しい用語を避けて負担なく読めるようにまとめていますので、苦手意識のある方もぜひ目を通してみてください。
Photo by Julius Silver: https://www.pexels.com/photo/white-water-boat-753331/
そもそも「関税」ってなに?
関税とは、海外から輸入される商品に対して国がかける特別な税金のことです。
この税金の目的はいくつかありますが、主だったものは以下の2点です。
- 国内の産業を守る
- 国の収入を増やす
まず、国内の産業を守るためです。
たとえば、もし海外からとても安い野菜や工業製品がたくさん入ってきたら、国内の農家や工場が売上を落としてしまうかもしれません。そこで、海外の商品に関税をかけて価格を少し高くすることで、国内の産業がすぐに負けないようにバランスをとっています。
もうひとつの目的は、国の収入を増やすことです。
国にとって、関税は重要な財源のひとつでもあります。
トランプ大統領が言う「相互関税」って?


トランプ大統領が言う相互関税とは、アメリカが他国から商品を輸入するときに、その国がアメリカ製品にかけているのと同じだけの関税をかけ返す、という考え方。「あなたの国がアメリカ製品に10%の関税をかけるなら、アメリカもその国の製品に10%の関税をかける」というイメージです。
この「相互関税(reciprocal tariffs)」という言葉は、実は一般的な経済用語ではありません。これは、トランプ大統領が2018年ごろから「公平な貿易」を訴える中で使うようになった、オリジナルの表現とされています。
相互関税の発想の背景には、「アメリカは今まで不公平な貿易を強いられてきた」というトランプ大統領の主張があります。「アメリカ製品には高い関税がかけられているのに、アメリカは他国製品をほとんど無税で受け入れている。不公平だ」というわけです。相互に同じ関税をかけることで、貿易のルールを「公平」にしよう、と訴えています。
一方で、実際の国際貿易では、各国の事情や交渉の歴史によって関税率が異なっているため、単純な「相互」に揃えることは、現実的には難しいという指摘もあります。単純に関税を合わせればすべてが公平になるわけではなく、むしろ摩擦が起きるリスクも考えられるでしょう。



ただし、トランプ大統領がこの政策で実現しようとしている社会については、もう少し英語の資料を読む必要があるかな、と感じています
ミニコラム:「関税」だけじゃない? 消費税が不公平感を生む理由
トランプ大統領が「アメリカは損をしている」と主張した背景には、各国の消費税(付加価値税/VAT)の仕組みもあります。
たとえば日本やヨーロッパでは、輸出品にかかる消費税を免除(または還付)しています。一方、アメリカはそもそも国レベルの消費税(VAT)がないため、こうした免税措置がありません。(※州ごとに「売上税(sales tax)」はあるが、VATとは違う仕組み)
この違いにより、アメリカ製品は海外で不利になり、逆に外国製品はアメリカ国内で有利になることがあるのです。
つまりトランプ氏は、関税だけでなく消費税の仕組みも含めて「不公平だ」と感じていた、というわけです。
🚢 輸出還付金≒「輸出補助金」
日本では、消費税は国内での消費に対して課税される「消費地課税」の原則に基づいています。そのため、輸出取引に関しては、消費税が免除され(輸出免税)、さらに仕入れ時に支払った消費税が還付される仕組みが採用されています。
この還付制度により、輸出企業は国内での仕入れにかかる消費税を実質的に負担せずに済むため、結果として政府が輸出業を支援している形になります。
実際、2022年度には、トヨタ自動車などの輸出大企業20社に対して、合計約1.9兆円の消費税還付が行われたと報告されています。
相互関税を強化するとどうなる?
「相互関税」を強化すると、国内の企業や産業を守る一方で、私たちの生活にも影響が出る可能性があります。ここでは、メリットとデメリットの両面から見ていきましょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ○自国企業を守れる ○交渉のカードになる | ×輸入品が高くなって物価上昇のリスク ×貿易相手国との関係悪化 |
メリット:自国企業を守れる、交渉のカードになる
関税を強化すると、海外から安い商品が入りにくくなり、国内の企業や産業を守ることができます。特に農業や製造業など、価格競争が厳しい分野では、大きな支えになります。
また、相互関税は国際交渉の場でも「カード」として使われます。たとえば「こちらが関税を下げる代わりに、あなたの国もこうしてね」と交渉を有利に進める材料になるのです。
デメリット:輸入品が高くなって物価上昇のリスク、貿易相手国との関係悪化
一方で、関税が上がると、輸入品の価格が高くなります。
外国から入ってくる食べ物や衣類、家電製品などの値段が上がり、結果的に私たち消費者の負担が増えるリスクがあります。
さらに、関税をかけられた国は「うちもかけ返すぞ!」と報復関税をすることがあり、国と国との関係が悪化することも。これが広がると、「貿易戦争」と呼ばれる経済的な対立に発展してしまうおそれもあります。
ミニコラム:2025年4月末時点の「相互関税」一覧
2025年4月、トランプ政権は「相互関税」政策を強化し、ほぼすべての国からの輸入品に対して10%の基本関税を導入しました。 さらに、貿易赤字が大きい国やアメリカ製品に高い関税を課している国には、より高い国別関税が適用されています。 以下は、主要国に対する2025年4月現在の関税率の一覧です。



交渉などで変動していますので、参考としてご覧ください
| 国・地域名 | 税率(%)▼ | 備考 |
|---|---|---|
| 中国 | 145% | 既存の関税に加え、追加関税を適用。 |
| 香港 | 145% | 中国と同様の扱い。 |
| ベトナム | 46% | 猶予期間あり、2025年7月9日以降適用予定。 |
| カンボジア | 49% | |
| スリランカ | 44% | |
| バングラデシュ | 37% | |
| タイ | 36% | |
| 台湾 | 32% | |
| インドネシア | 32% | |
| スイス | 31% | |
| 南アフリカ | 30% | |
| パキスタン | 29% | |
| インド | 26% | |
| 韓国 | 25% | |
| 日本 | 24% | |
| 欧州連合(EU) | 20% | |
| イスラエル | 17% | |
| オーストラリア | 10% | 標準税率。 |
| イギリス | 10% | |
| ウクライナ | 10% | |
| シンガポール | 10% | |
| カナダ | 0% | USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定、旧NAFTA)に基づき免除。 ※特定の品目を除いて関税の対象外。 |
| メキシコ | 0% |
このように、関税率は国や地域ごとに大きく異なり、アメリカの貿易政策の複雑さを反映しています。 特に中国やベトナムなど、一部の国に対しては非常に高い関税が課されており、国際貿易に大きな影響を与えています。
📚この情報は、以下の資料を参考にしています:
- Trump Reciprocal Tariff – Wikipedia
- President Trump Announces New “Reciprocal Tariffs” for Almost All Imports into the United States | Haynes Boone
- Trump Reduces Global Reciprocal Tariffs but Increases Them for China | Wiley Rein LLP – JDSupra
- Trade Action Update: Reciprocal Tariffs Paused for 90 Days; Ten Percent Tariff on All Countries Remains in Effect; China Tariffs Increased | Baker Donelson
日常生活への影響
相互関税が強化されると、実際の私たちの暮らしにはどのような影響があるでしょうか。
まず、海外から輸入される食品や服、電化製品などが、関税の影響で値上がりするかもしれません。たとえば、海外ブランドのチョコレートやワイン、アメリカ製のカジュアルウェア、スマートフォンなど、今より高くなるリスクがあります。
また、自動車のような高額な買い物にも注意が必要です。輸入車だけでなく、部品を海外から仕入れている国産車も、コスト増により価格が上がる可能性があります。
一方で、海外製品の価格が上がることで、国産品に注目が集まるチャンスにもなります。たとえば、国産の野菜や果物、国内ブランドの家電製品に目を向ける人が増え、日本の産業が元気を取り戻すきっかけになるかもしれません。
とはいえ、物価全体が押し上げられると、家計にとっては負担となるため、今後の動きには注意が必要です。
アメリカから輸入している品物


以下は、日本がアメリカから輸入している主要な農産物トップ5とその数量(2020年)の一覧です。
| 順位 | 品目 | 輸入量(概算) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | トウモロコシ | 約1,846万トン | 主に飼料用。日本は世界第2位のトウモロコシ輸入国。 |
| 2 | 大豆 | 約3.4百万トン | 食品加工や飼料用に使用。 |
| 3 | 小麦 | 約70万トン | パンや麺類の原料として使用。 |
| 4 | 牛肉 | 約1,944百万ドル相当 | 日本は米国産牛肉の最大の輸出先。 |
| 5 | 豚肉 | 約1,626百万ドル相当 | 日本は世界最大の豚肉輸入国の一つ。 |
これらの農産物は、日本の食料供給において重要な役割を果たしています。特に、トウモロコシや大豆は飼料や食品加工の原料として不可欠であり、牛肉や豚肉は日本の食卓に欠かせないタンパク源となっています。
工業資材はどうでしょうか。以下は、2023年時点で日本がアメリカから輸入している主要な工業資材トップ5とその輸入額の一覧です。
| 順位 | 品目 | 輸入額(2023年) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 機械類(原動機、ポンプ等) | 約57億ドル | 製造業や建設業で使用される各種機械類。 |
| 2 | 電子機器 | 約50億ドル | コンピュータ、通信機器、半導体など。 |
| 3 | 航空機・宇宙機器 | 約48億ドル | 航空機やその部品、宇宙関連機器。 |
| 4 | 有機化学品 | 約23億ドル | 化学工業や製薬業で使用される各種化学品。 |
| 5 | プラスチック製品 | 約21億ドル | 各種プラスチック材料や製品。 |
これらの工業資材は、日本の製造業や建設業など多くの産業で不可欠な役割を果たしています。特に、機械類や電子機器は、製品の生産やインフラの整備において重要な部品や装置として使用されています。



相互関税が高くなると、食品や製品の値上げが心配です
まとめ
とりあえず、7月までは猶予もあるらしい相互関税。ただし、「相互関税」の名のもとに追加関税が次々と出される可能性もあり、今後の交渉の行方にも注意が必要です。
また、日本や他の国々がどう対応するかも重要なポイントです。もしアメリカに対して報復関税をかける動きが強まれば、世界の貿易関係はさらに緊張し、経済全体にも影響が広がっていくかもしれません。
そして何より、私たちの日常生活への影響にも敏感になりたいところです。輸入品の価格上昇が続けば、食料品や日用品、家電製品など、身近なものの値段が上がる可能性があります。「最近なんだか高くなったな」と感じたときは、もしかしたら国際情勢が背景にあるのかもしれません。



これからも、ニュースや商品価格の変化にアンテナを立てて、賢く暮らしていきたいですね!
📚 主な参考記事
- JETRO 貿易・投資相談Q&A – 輸出時の消費税:日本(最終更新:2024年12月)
- 全国商工新聞「22年度 トヨタなど輸出大企業20社に消費税還付1.9兆円」(2023年11月27日付)
- Japan 2020 Export Highlights | USDA Foreign Agricultural Service
- 4 Major Food Imports In Japan
- Top 10 US Exports to Japan – Source From USA
- Office of the United States Trade Representative(USTR)公式サイト
- Bloomberg|トランプ氏、関税猶予の再延長に否定的-日本との合意「非常に近い」



ありがとうございます



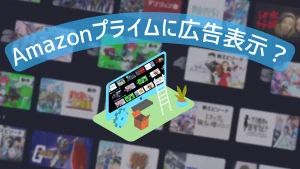
コメント